
消費税が日本経済と社会に与える悪影響――石田和也氏×深田萌氏対談まとめ
経済問題の専門家・石田和也氏と深田萌絵氏による対談では、消費税が日本経済、特に中小企業や雇用、さらには少子高齢化や外国人による犯罪にまで及ぼす深刻な影響について、具体的な事例とともに議論が交わされました。
以下、主なポイントをまとめます。
消費税による雇用の破壊
石田氏は、消費税制度が企業の雇用形態に与えている影響について指摘しています。消費税の計算において正社員の給与は課税対象外である一方、非正規雇用の外注費は仕入れ税額控除の対象となります。
そのため、企業は消費税負担を軽減する目的で、正社員から非正規雇用への切り替えを進める傾向が強まっています。
この流れは、非正規雇用の増加や賃金の低下、社会保障の未整備、退職金の不支給といった問題を引き起こし、結果として少子高齢化の進行にもつながっていると石田氏は述べています。
業務効率の悪化と労働生産性の低下
消費税はほぼすべての取引に課税されるため、企業の経理業務は消費税計算や控除の処理で複雑化しています。
特に中小企業では、会計ソフトの導入が進んでいないケースも多く、手作業での計算が大きな負担となっています。
さらに、インボイス制度の導入によって、消費税計算の複雑さは増し、より多くの企業が業務効率の悪化を余儀なくされています。
石田氏は、こうした状況が日本全体の労働生産性低下を招いていると警鐘を鳴らします。
外国人による消費税の悪用と犯罪の助長
石田氏は、輸出免税制度を利用した外国人による消費税還付の悪用事例を紹介しています。具体的には、外国人が日本で会社を設立し、商品を輸出して消費税の還付金を受け取る。
その還付金を担保に銀行から資金を借り入れ、還付金と借入金を持って海外へ逃亡するという詐欺行為が横行しているといいます。
この問題について政府も認識はしているものの、十分な対策が講じられていない現状を石田氏は批判しています。
提案と解決策
石田氏は、消費税が非効率を生み出し、中小企業の生産性を低下させている元凶であるとして、消費税の廃止を提言しています。
また、国会議員や財務省職員も自ら事業所得者として消費税の計算や納税の困難さを体験すべきだと主張。
法人税は経済を回す効果があるため、法人税を上げて消費税を廃止するべきだとしています。
まとめ
この対談では、消費税が日本社会のさまざまな問題とどのように結びついているかが、具体的な事例を交えて深く掘り下げられました。
雇用の質の低下や業務効率の悪化、制度悪用による犯罪など、消費税がもたらす負の側面について改めて考えるきっかけとなる内容です。
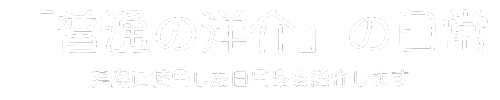














































コメント