
『この国でそれでも生きていく人たちへ』(講談社+α新書)をブログで紹介するための解説
森永卓郎・森永康平による本書は、激動の時代を生き抜くための知恵と心構えを、親子対談形式で語り合う一冊です。特に日本社会の「重税」問題については、現場感覚と経済アナリストとしての鋭い視点から、現状の矛盾や理不尽さを浮き彫りにしています。
日本の重税――その「おかしさ」と現実
国民負担率の異常な上昇
日本では、国民負担率(税金+社会保険料の合計)が2022年に47.5%と、実に「五公五民」(収入の半分近くが国に取られる)に迫る水準にまで上昇しています。
この負担増の主な要因は、2014年・2019年の消費税増税による税負担の急拡大です。
消費税の「逆進性」と経済への悪影響
消費税は、所得に関係なく一律に課されるため、低所得者ほど生活への負担が重くなる「逆進性」が指摘されています。
さらに、消費税率引き上げは、個人消費を冷え込ませ、景気悪化や中小業者の経営悪化を招いてきました。
「二重課税」の実態
ガソリンや酒、たばこなどには、個別の税金が課されているにもかかわらず、その税金を含んだ価格にさらに消費税がかかる「二重課税」も大きな問題です。
たとえばガソリンの場合、ガソリン税を含む価格に消費税が上乗せされており、消費者は「税金に税金を払う」構造になっています。
社会保険料の重さ
日本の「重税感」は、所得税や消費税だけでなく、社会保険料の負担が大きいことにも起因します。
国民健康保険や年金保険などの社会保険料は、医療や年金制度を支えるために不可欠とはいえ、現役世代や若者にとっては重い負担となっています。
重税がもたらす社会への影響
本書のメッセージと「生き抜く知恵」
森永親子は、こうした「重税国家」の現実を冷静に分析しつつ、絶望せずに生き抜くための知恵や心構えを提案しています。
政府やエリート層による搾取、階級社会の固定化、自己責任論の蔓延など、現代日本の「おかしさ」に真っ向から切り込み、「それでも生きていく」ための現実的なアドバイスを展開しています。
まとめ:なぜ今この本を読むべきか
にとって、本書は必読の一冊です。森永親子の率直な対話を通じて、「重税国家・日本」で賢く生き抜くためのヒントを、ぜひ手に取ってみてください。
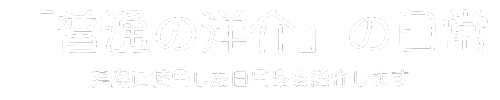













































![この国でそれでも生きていく人たちへ【電子書籍】[ 森永卓郎 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9213/2000017039213.jpg?_ex=128x128)


コメント